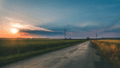行政書士の申請登録を9月17日に控え、今日はどのように自分が行政書士及び社労士の資格勉強対策を行っていたかを思い出していました。
私は社会保険労務士を2012年に、行政書士を2018年に取得しています。社会保険労務士は3度目で合格、行政書士は一発で合格することができました。
試験勉強について、確かに両方とも暗記すべきことは多いですが、勉強としては圧倒的に行政書士のほうが面白いです。特に民法は、仕事や生活上の役にも立ちます。一度仕事で役に立ったのが、ある動画編集ソフト利用の契約をした際、オプションサービスを先方の担当者が無料で使わせると口約束をしていましたが、実際、導入後は基本サービスのみとなっていました。そこで、担当者にメールで「契約上の齟齬があるので、契約を無効にしたい」と伝えたら、その担当者と責任者が飛んできました。結局、担当者の言ったとおり、オプションも無料で提供していただけることとなりました。これは、民法「契約」で学んだことです。
社会保険労務士の勉強は、本当に面白くないです。ただ、暗記に尽きます。当時私は、外国人関係の労務管理等についての仕事に携わっていたため、社労士の資格はどうしても欲しかったのです。当時は開業のためではなく、仕事の役に立たせるためです。でも試験勉強は本当に辛かったです。
試験勉強は、行政書士・社労士とも、私の場合は、過去問の勉強が8割を占めました。講義受講後、家でノートに重要事項を復習がてら記載し、あとはひたすら過去問を解いていました。同じ問題を何回でも何回でも。通勤時、会社の昼休み等暇を見つけては過去問を解いていました。そうすると、わからない問題でも、自然に回答の予想がつくようになります。
行政書士受験の際は、すでに結婚をしており、妻の助けがあったので一発合格できたと思っています。
資格試験は、基本講義を終えたら一回復習し、あとは過去問をやりまくるのが一番の合格への近道と思っています。どうしても理解できないことがあれば、教科書に戻ればいいのです。これから受験される皆様には参考になるかわかりませんが、問題を解く癖をつけたほうがいいのは確かです。
行政書士・社会保険労務士のダブル資格を目指している方がいらっしゃれば、参考にしていただければと思うですが、私は先に社労士を合格して、次に行政書士試験を受けましたが、順序的には、社労士→行政書士のほうがいいと思います。
社労士は、完全暗記の世界で、各科目ごとに足切りがあります。行政書士も足切りはありますが、科目ごとにはありません。法令と一般知識の2種類での足切りです。
社会保険労務士は、労働基準法から始まり、すべての科目に足切りがあります。そのため、この法律科目は捨てるといったようなことができません。すべての科目をある程度勉強する必要があります。
この観点から、社会保険労務士の試験のほうが難易度は高いと思っています。社労士の試験を合格したら、少し自信をつけたところで行政書士試験を受ける流れのほうがいいのかなと、私自身の体験・感覚でそう思いました。
でも、勉強の仕方等も人それぞれ自分に合う・合わないがあると思いますが、過去問だけは、死ぬほどやることが合格への近道であると断言できます。
開業を目指す人は、合格することがゴールですが、行政書士・社労士とも勉強すれば、かなり社会人の知識として役に立ちます。当初の私がそうであったように、会社の管理部門に従事されている方は、業務のために勉強し受験するのもいいと思います。